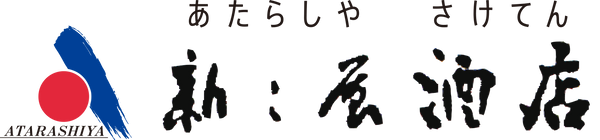発酵セミナー腸活Blog

11/14 八海山発酵セミナー【醬油麴編】レポート
朝晩の気温がぐっと低くなってきた11月半ば、近所のイチョウの木がきれいな黄色にいろづいて秋の深まりを感じます。寒さに向かうこれからの時期、発酵調味料を上手く使って元気に過ごしましょう!ということで・・・今回の発酵セミナーは「醤油麹」。 醤油の種類は、JAS規格で分かれていることを知っていますか。その分類を聞いて質問が出ました。それは、お餅を食べるときの醤油について。 「お餅に一番合う美味しい醤油ってどれなのか?問題」・・・これからのシーズンに気になるポイントです。みんなで盛り上がりましたよ。 醤油はとても身近なのに、原料は何かを知らない人が意外と多いそう。私も発酵マイスターの勉強をするまでは、考えたこともありませんでした。それが今では冷蔵庫に何種類もの醤油が入っているという変わりよう(笑) そんな私に影響されて⁉家族も醤油を使い分けるようになってきました。 今回の試食 ・レンコンの醤油麹混ぜご飯 ・鶏むね肉の唐揚げ ・ニンジンの醤油麹カレーきんぴら 今回の発酵セミナーの感想 ・醬油麴、こんなに簡単に作れるとは!びっくりしました。使うのが楽しみです。麹は好きだけど、詳しいことは全くわからなかってので、とても勉強になりました。もっと学んでみたいと思いました。 ・醤油麹、ずっと気になっていたので、学べて嬉しいです! ・醤油麹作るのが楽ちんで感激しました。簡単でおいしいのがありがたいです。 など、他にも嬉しい感想をたくさんいただきました。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。
11/14 八海山発酵セミナー【醬油麴編】レポート
朝晩の気温がぐっと低くなってきた11月半ば、近所のイチョウの木がきれいな黄色にいろづいて秋の深まりを感じます。寒さに向かうこれからの時期、発酵調味料を上手く使って元気に過ごしましょう!ということで・・・今回の発酵セミナーは「醤油麹」。 醤油の種類は、JAS規格で分かれていることを知っていますか。その分類を聞いて質問が出ました。それは、お餅を食べるときの醤油について。 「お餅に一番合う美味しい醤油ってどれなのか?問題」・・・これからのシーズンに気になるポイントです。みんなで盛り上がりましたよ。 醤油はとても身近なのに、原料は何かを知らない人が意外と多いそう。私も発酵マイスターの勉強をするまでは、考えたこともありませんでした。それが今では冷蔵庫に何種類もの醤油が入っているという変わりよう(笑) そんな私に影響されて⁉家族も醤油を使い分けるようになってきました。 今回の試食 ・レンコンの醤油麹混ぜご飯 ・鶏むね肉の唐揚げ ・ニンジンの醤油麹カレーきんぴら 今回の発酵セミナーの感想 ・醬油麴、こんなに簡単に作れるとは!びっくりしました。使うのが楽しみです。麹は好きだけど、詳しいことは全くわからなかってので、とても勉強になりました。もっと学んでみたいと思いました。 ・醤油麹、ずっと気になっていたので、学べて嬉しいです! ・醤油麹作るのが楽ちんで感激しました。簡単でおいしいのがありがたいです。 など、他にも嬉しい感想をたくさんいただきました。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。

assh10月号の特集は「腸活のすすめ」
「腸活」がブームになってどれくらいになるでしょうか。 新し屋酒店の2階で【八海山発酵セミナー】を始めて10年 日本発酵文化協会の発酵マイスターの資格を取得して8年 そのなかで「腸活」がとても大切なことを知ってから、みんなに「腸活って大事なんだよ!」と連呼していたら(無意識⁉)、同じことを言っている人がいると紹介されたのが、松田さん(えくみん)でした。それが、Niigata腸活部の始まりです。 今回、asshさんにNiigata腸活部のことを取材していただきました。Web magazine asshを見てもらえると嬉しいです。 えくみんと2人のユニットですが、私たちを会わせてくれた大切な友人もNiigata腸活部の仲間です。ひとりではできないことも、仲間が一緒ならがんばれる。けれど無理はしない。ゆるゆる楽しく続けることをこれからも大切にしていこうと改めて思いました。 いろいろな発酵食品を毎日取り入れること、続けることで、半年後、1年後、1年半後に「しばらく風邪ひいていないよね」「お通じがよくなってるかも」「疲れにくくなったかな」「お肌がきれいになったかも」等々の変化を感じられるようになると思います。 日本発酵文化協会の藤本先生からの「発酵食品は継続することが大切!」という教えを、そっくりそのまま皆さんにいつも伝えています。 Niigata腸活部の活動も、発酵食品を取り入れて腸内環境を整える腸活も、ムリしない。楽しみながらゆるゆるとです。
assh10月号の特集は「腸活のすすめ」
「腸活」がブームになってどれくらいになるでしょうか。 新し屋酒店の2階で【八海山発酵セミナー】を始めて10年 日本発酵文化協会の発酵マイスターの資格を取得して8年 そのなかで「腸活」がとても大切なことを知ってから、みんなに「腸活って大事なんだよ!」と連呼していたら(無意識⁉)、同じことを言っている人がいると紹介されたのが、松田さん(えくみん)でした。それが、Niigata腸活部の始まりです。 今回、asshさんにNiigata腸活部のことを取材していただきました。Web magazine asshを見てもらえると嬉しいです。 えくみんと2人のユニットですが、私たちを会わせてくれた大切な友人もNiigata腸活部の仲間です。ひとりではできないことも、仲間が一緒ならがんばれる。けれど無理はしない。ゆるゆる楽しく続けることをこれからも大切にしていこうと改めて思いました。 いろいろな発酵食品を毎日取り入れること、続けることで、半年後、1年後、1年半後に「しばらく風邪ひいていないよね」「お通じがよくなってるかも」「疲れにくくなったかな」「お肌がきれいになったかも」等々の変化を感じられるようになると思います。 日本発酵文化協会の藤本先生からの「発酵食品は継続することが大切!」という教えを、そっくりそのまま皆さんにいつも伝えています。 Niigata腸活部の活動も、発酵食品を取り入れて腸内環境を整える腸活も、ムリしない。楽しみながらゆるゆるとです。
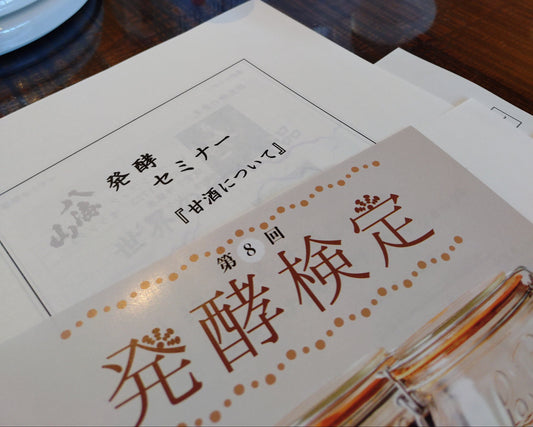
9/26 八海山発酵セミナー【甘酒調味料編】レポート
9月に入ってもしばらくは夏のような暑さでしたが、最近は朝晩ずいぶん涼しくなってきました。この時期、夏の疲れを感じている人もいるのでは...今回の発酵セミナーは「飲む点滴」とも言われている「甘酒」。 「甘酒」には、麹の酵素を利用した発酵で作る砂糖不使用・ノンアルコールの甘酒と、酒粕を使って作る甘酒の2種類があること。麹バージョンの甘酒の成分や、酒粕についても学んでいきます。 甘酒を使った調味料つくりは、とても簡単!その上お持ち帰りしたら、即使うことができるのも「甘酒調味料」のいいところです。 今回の試食 ・チキンテリヤキ ・ホタテの甘酒味噌バター焼き ・ゆで卵の甘酒味噌漬け ・にんじんとドライマンゴーのサラダ ・大根の甘酒酢漬け 今回の発酵セミナーの感想 ・甘酒について学べて楽しかったです。飲むだけでなく、食事にも使えるのは知っていましたが手を出せず…今回使う方法が分かって良かったです ・甘酒にも種類があることをはじめて知りました。レシピもすぐ作れそうなものばかりで参考になります ・味噌×甘酒の調味料、さっそくお気に入りです‼ など、他にも嬉しい感想をたくさんいただきました。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。
9/26 八海山発酵セミナー【甘酒調味料編】レポート
9月に入ってもしばらくは夏のような暑さでしたが、最近は朝晩ずいぶん涼しくなってきました。この時期、夏の疲れを感じている人もいるのでは...今回の発酵セミナーは「飲む点滴」とも言われている「甘酒」。 「甘酒」には、麹の酵素を利用した発酵で作る砂糖不使用・ノンアルコールの甘酒と、酒粕を使って作る甘酒の2種類があること。麹バージョンの甘酒の成分や、酒粕についても学んでいきます。 甘酒を使った調味料つくりは、とても簡単!その上お持ち帰りしたら、即使うことができるのも「甘酒調味料」のいいところです。 今回の試食 ・チキンテリヤキ ・ホタテの甘酒味噌バター焼き ・ゆで卵の甘酒味噌漬け ・にんじんとドライマンゴーのサラダ ・大根の甘酒酢漬け 今回の発酵セミナーの感想 ・甘酒について学べて楽しかったです。飲むだけでなく、食事にも使えるのは知っていましたが手を出せず…今回使う方法が分かって良かったです ・甘酒にも種類があることをはじめて知りました。レシピもすぐ作れそうなものばかりで参考になります ・味噌×甘酒の調味料、さっそくお気に入りです‼ など、他にも嬉しい感想をたくさんいただきました。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。

7/18 八海山発酵セミナー 【食酢編】レポート
毎日30℃を越える暑さが続いて、体の疲れがたまっていませんか。暑い夏には「酢」がおすすめ!というタイミングで、今回のテーマは【食酢編】でした。 食酢編は、歴史の話から始まり、食酢の分類、製造方法などについて学んでいきます。 食酢編お持ち帰りの「麹ピクルス液」は、砂糖を使わず、あまさけでピクルス液を作ります。そこに好きな野菜を入れて3~6日くらいで食べごろになります。 ピクルスは、そのまま食べてもちろんおいしいですが、いろいろなソースにも使えます。ピクルス液はスープに入れると酸味がプラスで食欲がUPしますよ!いつも大好評の、簡単・時短で野菜がたっぷり摂れる一品です。 今回の試食 ・ピクルス(きゅうり、にんじん、セロリ、パプリカ) ・野菜とウインナーのピクルススープ ・タルタルソースピクルス入り ・さっぱりオーロラソースピクルス入り ・エビフライ、ポテトフライ 今回の発酵セミナーの感想 ・発酵にはとても興味があって、今回参加できてよかったです。「酢がどうやってできているのか」から知ることができておもしろかったです ・ピクルスからのアレンジもたくさんで、レパートリーが増えそうです ・普段あまり深く考えずに酢を使っていましたが、何をどう使うか考えるきっかけになりました ・簡単に作れるレシピで今後も家で作れそうです など、他にも嬉しい感想をたくさんいただきました。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。
7/18 八海山発酵セミナー 【食酢編】レポート
毎日30℃を越える暑さが続いて、体の疲れがたまっていませんか。暑い夏には「酢」がおすすめ!というタイミングで、今回のテーマは【食酢編】でした。 食酢編は、歴史の話から始まり、食酢の分類、製造方法などについて学んでいきます。 食酢編お持ち帰りの「麹ピクルス液」は、砂糖を使わず、あまさけでピクルス液を作ります。そこに好きな野菜を入れて3~6日くらいで食べごろになります。 ピクルスは、そのまま食べてもちろんおいしいですが、いろいろなソースにも使えます。ピクルス液はスープに入れると酸味がプラスで食欲がUPしますよ!いつも大好評の、簡単・時短で野菜がたっぷり摂れる一品です。 今回の試食 ・ピクルス(きゅうり、にんじん、セロリ、パプリカ) ・野菜とウインナーのピクルススープ ・タルタルソースピクルス入り ・さっぱりオーロラソースピクルス入り ・エビフライ、ポテトフライ 今回の発酵セミナーの感想 ・発酵にはとても興味があって、今回参加できてよかったです。「酢がどうやってできているのか」から知ることができておもしろかったです ・ピクルスからのアレンジもたくさんで、レパートリーが増えそうです ・普段あまり深く考えずに酢を使っていましたが、何をどう使うか考えるきっかけになりました ・簡単に作れるレシピで今後も家で作れそうです など、他にも嬉しい感想をたくさんいただきました。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。

旬を楽しむ。手づくり豆板醤と梅ジャム
6月になると、毎年「そろそろ仕込まなきゃ」とそわそわしてくるものがあります。 ひとつ目は、2年前から作り始めた『豆板醤』づくり。 お世話になっている日本発酵文化協会の藤本先生のブログ、豆板醤はいましか仕込めない!を読んで、豆板醤を仕込む⁉ 自分で作る⁉ 興味津々でした。もう5年前のことです。 藤本先生のブログを読んでいたのに・・2年前、友人と『豆板醤』を作ろうとやる気スイッチがON!になった時は、「空豆」の旬が終わりかけ。 「空豆が欲しいんですけど」と、お世話になっている農家さんにお願いしたら「今ごろ~、もう空豆終わったよ」とさらりと言われて青くなった思い出⁉があります。その後、何とか見つけて『豆板醤』を作ることができました。 やはり自分で作ると美味しい。辛さの調節もできるので、辛さに弱い私はうれしいですね。そして、みんなで作ると楽しいです。発酵・熟成を待つのもわくわく。今年もNiigata腸活部の活動として、みんなで一緒に楽しく作りました。 ふたつ目は、梅仕事。今年は完熟梅で甘くない『梅ジャム』づくり。 発酵マイスター、発酵プロフェッショナルの資格を持つ榎本美沙さんの大人気YouTubeを見て作ってみました。動画は分かりやすくていいですね。 新し屋酒店のある新潟市江南区亀田地区は、県内でも有数の梅の産地です。「藤五郎梅」という品種は亀田発祥の品種なんです(数年前の梅の収穫体験で教えてもらいました)。梅には疲労回復、抗菌、整腸、抗酸化作用、解毒促進など様々な効果が期待できると言われています。 完熟梅とハチミツだけで作る甘くない『梅ジャム』は、ヨーグルトに添えて、パンのお供に、あっという間になくなりそうです。
旬を楽しむ。手づくり豆板醤と梅ジャム
6月になると、毎年「そろそろ仕込まなきゃ」とそわそわしてくるものがあります。 ひとつ目は、2年前から作り始めた『豆板醤』づくり。 お世話になっている日本発酵文化協会の藤本先生のブログ、豆板醤はいましか仕込めない!を読んで、豆板醤を仕込む⁉ 自分で作る⁉ 興味津々でした。もう5年前のことです。 藤本先生のブログを読んでいたのに・・2年前、友人と『豆板醤』を作ろうとやる気スイッチがON!になった時は、「空豆」の旬が終わりかけ。 「空豆が欲しいんですけど」と、お世話になっている農家さんにお願いしたら「今ごろ~、もう空豆終わったよ」とさらりと言われて青くなった思い出⁉があります。その後、何とか見つけて『豆板醤』を作ることができました。 やはり自分で作ると美味しい。辛さの調節もできるので、辛さに弱い私はうれしいですね。そして、みんなで作ると楽しいです。発酵・熟成を待つのもわくわく。今年もNiigata腸活部の活動として、みんなで一緒に楽しく作りました。 ふたつ目は、梅仕事。今年は完熟梅で甘くない『梅ジャム』づくり。 発酵マイスター、発酵プロフェッショナルの資格を持つ榎本美沙さんの大人気YouTubeを見て作ってみました。動画は分かりやすくていいですね。 新し屋酒店のある新潟市江南区亀田地区は、県内でも有数の梅の産地です。「藤五郎梅」という品種は亀田発祥の品種なんです(数年前の梅の収穫体験で教えてもらいました)。梅には疲労回復、抗菌、整腸、抗酸化作用、解毒促進など様々な効果が期待できると言われています。 完熟梅とハチミツだけで作る甘くない『梅ジャム』は、ヨーグルトに添えて、パンのお供に、あっという間になくなりそうです。

5/16 八海山発酵セミナー【塩麴編】レポート
八海山発酵セミナーのシーズン10は、塩麴編からのスタートでした。 今回から平日開催になり、参加してくれた方の大半が20代、30代で、若い世代の皆さんが【発酵調味料】に興味を持ってくれたことがとても嬉しかったです。 八海山発酵セミナーは、どの講座(みりん編を除く)も最初に「アスペルギルス属の図」から話が始まります。麹を使って何ができるかと、発酵には順番があることが分かりやすい図になっています。この図から、麹が日本の食卓にはとても大事だということがよくわかります。 塩麴編は、「発酵」とは?から、世界の発酵食品、日本の発酵食品、発酵食品の効果、「麹」とは?など・・・知って得することが盛りだくさん! 皆さん、どんどん発酵食品・発酵調味料の魅力に引き込まれて楽しそうでした♪ 自分で塩麴を作るのはハードルが高いと思っていた方も、話を聞いた後はこれならできる!と…その上自分で作れば塩分濃度も自分で決めることができるので、使い勝手も良い!はずです。自分で決めた塩分濃度で作った塩麴は、毎日忙しいなかでの料理作りの助っ人になってくれると思います。 今回の発酵セミナーの感想には ・麹が気になっていたので、詳しく知ることができてよかったです ・簡単に塩麴が作れるようになって、麹が身近になりました ・これからは塩麴を手作りしていきたいです など、他にも嬉しい感想をたくさんいただきました。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。 ★次回の八海山発酵セミナーは、食酢編です。7月18日㈮10時30分~12時です。 ご興味がある方は、こちらからお申し込みください。 新し屋酒店:025-382-2345
5/16 八海山発酵セミナー【塩麴編】レポート
八海山発酵セミナーのシーズン10は、塩麴編からのスタートでした。 今回から平日開催になり、参加してくれた方の大半が20代、30代で、若い世代の皆さんが【発酵調味料】に興味を持ってくれたことがとても嬉しかったです。 八海山発酵セミナーは、どの講座(みりん編を除く)も最初に「アスペルギルス属の図」から話が始まります。麹を使って何ができるかと、発酵には順番があることが分かりやすい図になっています。この図から、麹が日本の食卓にはとても大事だということがよくわかります。 塩麴編は、「発酵」とは?から、世界の発酵食品、日本の発酵食品、発酵食品の効果、「麹」とは?など・・・知って得することが盛りだくさん! 皆さん、どんどん発酵食品・発酵調味料の魅力に引き込まれて楽しそうでした♪ 自分で塩麴を作るのはハードルが高いと思っていた方も、話を聞いた後はこれならできる!と…その上自分で作れば塩分濃度も自分で決めることができるので、使い勝手も良い!はずです。自分で決めた塩分濃度で作った塩麴は、毎日忙しいなかでの料理作りの助っ人になってくれると思います。 今回の発酵セミナーの感想には ・麹が気になっていたので、詳しく知ることができてよかったです ・簡単に塩麴が作れるようになって、麹が身近になりました ・これからは塩麴を手作りしていきたいです など、他にも嬉しい感想をたくさんいただきました。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。 ★次回の八海山発酵セミナーは、食酢編です。7月18日㈮10時30分~12時です。 ご興味がある方は、こちらからお申し込みください。 新し屋酒店:025-382-2345